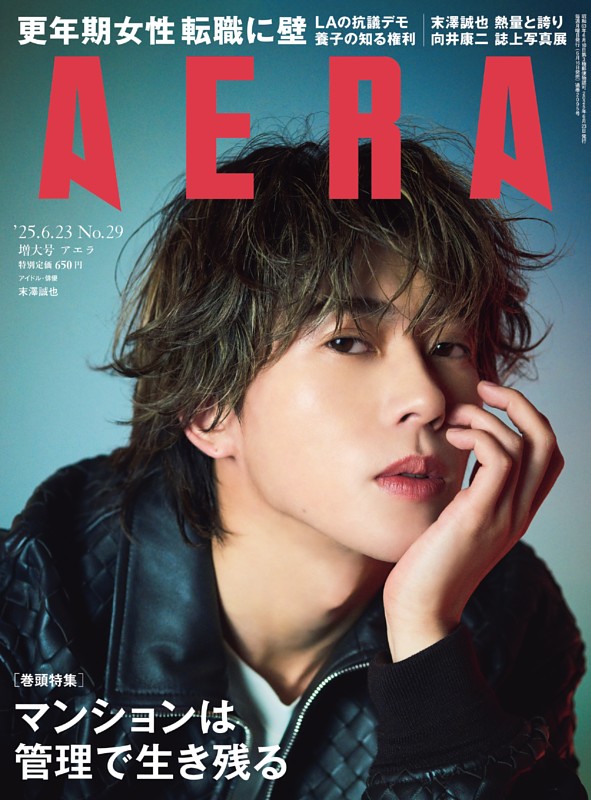マンションを売買する際、売主側が負うのが瑕疵担保責任または契約不適合責任です。売買したマンションに欠陥や不具合があった際に、売主はその責任を負う義務があります。瑕疵担保責任や契約不適合責任について正しく理解して、引き渡し後のトラブルに備えておきましょう。
本記事ではマンションの瑕疵担保責任や契約不適合責任が適用される要件や期間を解説します。瑕疵があるマンションの具体例も紹介するため、気になる不具合がある方もぜひ参考にしてください。
目次
中古マンションにおける瑕疵担保責任と契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、これまでは売主の瑕疵担保責任として扱われており、令和2年4月1日に民法改正に伴い、契約不適合責任へと名称や内容が変更されました。令和2年4月1日以降の売買契約は契約不適合責任、令和2年3月31日以前は瑕疵担保責任が適用されることになります。
瑕疵担保責任と契約不適合責任が適用される要件と内容の違いをみていきましょう。
瑕疵担保責任の適用要件
瑕疵担保責任が適用されるのは、売主が知らなかった瑕疵(建物の不具合)が物件引き渡し後に見つかった場合です。
たとえば、売買時には把握していなかったが暮らしはじめてから雨漏りしているのを発見した、などが該当します。
売主はその瑕疵に対して、一定期間責任を負わなければいけません。ただし、売主が不具合を知っていたのに故意に伝えなかった場合は、決められた期間が過ぎていても責任を追及できます。
契約不適合責任の適用要件
契約不適合責任が適用されるのは、契約書に記載されている種類・品質(経年劣化は除く)・数量と引き渡されたマンションが適合していないときです。建物の仕様の違いも該当します。
瑕疵担保責任と異なり、売主が瑕疵を知っていたか知らなかったかは関係ありません。とはいえ、知らなかったことを理由に契約書に記載しておらず、実際と相違があったときは契約不適合責任をおうことになるため、建物の状態をしっかり把握しておくことが大切になります。
瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い
瑕疵担保責任と契約不適合責任は、適用要件のほか、責任追及の手段(どのように責任をとるか)と期間にも以下のような違いがあります。
| 瑕疵担保責任 | 契約不適合責任 | |
| 適用要件 | 買主の知らない瑕疵 | 契約内容との不適合 |
| 責任追及の手段 | ・損害賠償請求
・契約の解除 |
・追完請求
・代金減額請求 ・損害賠償請求 ・契約の解除 |
| 適用期間 | 瑕疵を知ったときから1年以内に請求 | 引き渡しから1年以内に不具合を通知 |
契約不適合責任は、瑕疵担保責任よりも責任追及の手段が増えます。1年以内に「請求」ではなく「通知」でよいこともあり、契約不適合責任のほうが、買主をより保護する内容になっているのが特徴です。
マンションの瑕疵担保責任(契約不適合責任)の追及手段

瑕疵担保責任(契約不適合責任)の追及手段について詳しく紹介します。
買主が売主に追及できるのは以下4つの権利です。
・追完請求※契約不適合責任のみ
・代金減額請求※契約不適合責任のみ
・損害賠償請求
・契約の解除
順に解説します。
追完請求※契約不適合責任のみ
追完請求は、契約書との相違点を契約書通りに直すことを求める権利です。不具合箇所を交換・修理したり、契約書通りの仕様に変更したりすることで、契約書と適合させます。
代金減額請求※契約不適合責任のみ
代金減額請求は、売主が追完請求に応じなかったときや追完請求が不可能なときに、売買代金の減額を求められます。
とくに居住するうえで必要不可欠な設備が壊れている場合、売主が修理や交換に応じなければ生活できません。売主側に直してもらえない場合は、代わりに売買代金を減額してもらい、修理費用に充当させるなどして買主側で対応します。
損害賠償請求
損害賠償請求は、瑕疵担保責任と契約不適合責任で少し内容が変わります。
瑕疵担保責任の場合は、売主に過失がなくても損害賠償請求できますが、対象は、契約が有効であると信じたことで発生した実費(信頼利益)の損害のみです。印紙や登記簿謄本の費用などが該当します。
契約不適合責任で損害賠償請求できるのは、売主に故意・過失がある場合のみです。また信頼利益に加え、予定通り売買が成立していれば発生していたはずの利益(履行利益)まで対象になります。たとえば購入したマンションを転売して得られる予定だった利益などです。
契約の解除
売主が追完請求および代金減額請求に応じない場合に、契約解除できる権利です。期間を設けて債務の履行を催促する催告解除と、期間を設けず契約を解除できる無催告解除の2種類あります。
売主が債務の履行を明らかに拒絶した場合や債務の履行が不可能と判断できるときは無催告解除できます。
マンションの瑕疵担保責任(契約不適合責任)の期間
瑕疵担保責任は瑕疵を知ったときから1年以内に請求しなければいけません。一方、契約不適合責任は、引き渡しから1年以内に不具合を通知し、請求は1年経過後でも可能です。
ただし、責任を追及できる期間は任意規定で、双方の合意によって変えられます。1年だと引渡しの前と後、いつ発生した不具合かの見極めが難しいため、個人の売主の場合は特約で3ヶ月程度の期間を定めているケースが大半です。
売主が不動産会社(宅建業者)の場合は、宅地建物取引業法により通知期間を2年以上とすることが定められています。
権利の時効期間は、瑕疵担保責任は引き渡しから10年、契約不適合責任は10年または買主がその事実を知ってから5年です。
瑕疵担保責任(契約不適合責任)が考えられるマンション事例
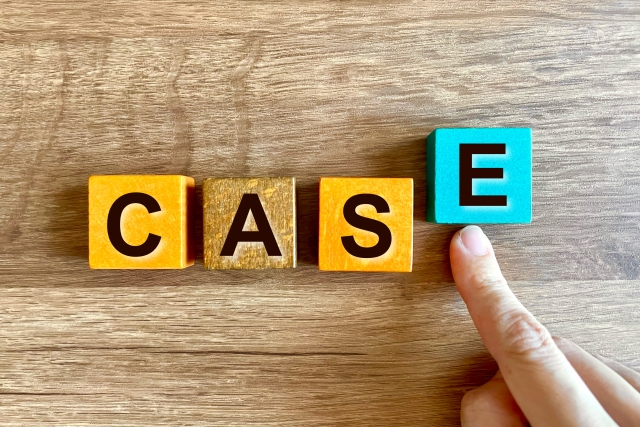
瑕疵担保責任や契約不適合責任の適用要件となる可能性があるのは、以下4つ瑕疵があるマンションです。
・破損や耐震不足などの「物理的瑕疵」がある
・事故物件のような「心理的瑕疵」がある
・法律や条例で制限される「法律的瑕疵」がある
・周辺の環境が問題になる「環境的瑕疵」がある
順に解説します。
破損や耐震不足などの「物理的瑕疵」がある
マンションそのものに物理的な瑕疵があるケースです。おもにマンションに「住む」という目的に影響を与える不具合を指します。
具体的には雨漏り・耐震不足・外壁ひび割れ・配管のつまりなどが該当し、専門家の調査により明らかになるケースが多いです。
事故物件のような「心理的瑕疵」がある
設備や構造などには問題なく安全に住めたとしても、心理的に不愉快になるような事項があれば、瑕疵となります。
マンション内での殺人や自殺、長期発見されなかった孤独死などが挙げられます。一般的に自然死や病死は該当しません。
法律や条例で制限される「法律的瑕疵」がある
現状問題なくマンションに居住できても、法律的な制限があると法律的瑕疵にあたります。
接道義務や容積率・建ぺい率違反などで、再建築した場合に同程度のマンションを建てられないケースは、事前に説明しておかなければいけません。
周辺の環境が問題になる「環境的瑕疵」がある
マンションそのものではなく、周辺環境に問題がある場合は環境的瑕疵と呼ばれています。
たとえばマンション近隣に、暴力団施設・廃棄物処理場・火葬場があるケースです。また健康被害が出るほど鉄道や車両などの騒音がある場合も環境的瑕疵に該当する可能性があります。
新築マンションなら築10年まで品確法の瑕疵担保責任が適用される
新築マンションなら、築10年目まで品確法の瑕疵担保責任が適用になります。
民法上の瑕疵担保責任は契約不適合責任に変更されましたが、品確法では瑕疵担保責任の定めが残っているのです。
品確法の瑕疵担保責任では、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものに限り、瑕疵を知ってから1年以内に通知すれば、引き渡しから10年間責任追及できます。
この規定に反して期間を短くするなど、注文者に不利な特約は無効です。
マンションの瑕疵や契約不適合によるトラブル防止策

マンションの瑕疵や契約不適合によるトラブルは意外に多いです。ここでは3つのトラブル防止策を紹介します。
・購入・売却前にホームインスペクションを活用する
・売買契約書の内容をこまかくチェックする
・瑕疵保険に加入する
順にみていきましょう。
購入・売却前にホームインスペクションを活用する
売買契約後に把握していなかった瑕疵が発見されることがないように、しっかりマンションの状態をチェックしておくことが大切です。
ホームインスペクションで、住宅診断士に劣化状態や欠陥の有無などを調べてもらいましょう。ホームインスペクションは売主だけでなく買主が依頼することも可能です。費用はかかりますが、引き渡し後のトラブルの発生リスクを下げられ、安心して新しい生活をスタートできます。
売買契約書の内容をこまかくチェックする
売買契約書の内容を細かくチェックすることも重要です。とくに契約不適合責任は、契約書の内容との相違があるかによって、責任追及の可否が変わります。
引き渡し後、不具合が見つかったり契約前の話と違ったりすることがあれば、まずは契約書の内容を確かめてください。また通知期間についても必ず確認し、タイミングを逃さないように注意しましょう。
瑕疵保険に加入する
瑕疵などの不具合に備えて、瑕疵保険に加入しておくのもよいでしょう。瑕疵保険はマンションの検査を依頼する事業者が加入する保険です。検査をしたうえで、マンション引き渡し後に瑕疵が見つかった場合に、検査をした事業者に保険金で、補修してもらえます。
瑕疵によるトラブルを未然に防止できるため、瑕疵保険について検査事業者に相談しておきましょう。
意外に多い!マンション共用部の瑕疵や欠陥はアフターサービスで対応できる

専有部だけでなく、共用部においても瑕疵や欠陥が見つかることが多々あります。
マンションの共用部は、分譲会社が定めるアフターサービス規準で、品確法と同じように、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の不具合が規定されており、費用負担なしで修繕してもらえるのです。
ただし、品確法の瑕疵担保責任やアフターサービスは、中古で購入した方には適用されません。しかし、共用部は区分所有者の共有持ち分のため、管理組合に内容を報告し、しかるべき対応を求めていくなどして、マンション管理に携わっていきましょう。
アフターサービスについては下記記事で詳しく解説しているため、参考にしてください。
【事例】外壁タイル剥落で施工時の不具合が発覚
外壁タイルが剥落したことをきっかけに、施工時の不具合が発覚した事例を紹介します。
外壁タイルが剥落を補修していた外壁を調査していたところ、鉄筋コンクリート構造体に瑕疵があることがわかりました。補修するためには、工事費に加え仮住まい費用まで必要で多額になることから、分譲会社は費用負担などに対し、難色を示していました。
さくら事務所にご相談いただき、状況を精密に検査。分譲会社らと折衝を重ねた結果、管理組合の要望が通り、分譲会社らの費用負担で再入居できるようになりました。しかし、総戸数の25%は流通価格で分譲会社に買い取られることになり、すべて元通りとはいきませんでした。
施工時の不具合を立証し、分譲会社らと折衝するのは根気のいる作業です。共用部の瑕疵トラブルがあれば、第三者の専門家の力を借りて解決に努めましょう。
マンションの瑕疵担保責任(契約不適合責任)の理解を深めトラブルに備えよう

マンションの瑕疵担保責任は、令和2年4月1日の民法改正により契約不適合責任に変わりました。責任を追及する手段が増え、売主の責任の範囲が広くなっているのがポイントです。
瑕疵担保責任は、売主が知らない瑕疵について適用されますが、契約不適合責任は、契約書の内容と相違があれば適用されます。
品確法では現在も瑕疵担保責任が残っています。新築マンションの場合は、築10年まで、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に限り責任追及できることも覚えておきましょう。
マンションに瑕疵や欠陥が見つかり、分譲会社や施工会社とトラブルになっている場合は、さくら事務所の「マンションの瑕疵・欠陥トラブル解決サポート」がおすすめです。瑕疵や欠陥の調査から関係者との折衝まで、管理組合の皆さまをサポートいたします。
また、10年目のアフターサービスを最大限活用できる、共用部のアフター点検も実施中です。マンションの基礎・屋上・外壁・開口部など、10年保証の対象となる項目を第三者としてチェックします。
大規模修繕の実施時期を判断するためにもご利用いただけるため、お気軽にご相談ください。
以下の動画では築10年目までにマンションの管理組合で絶対にやった方がいいことを詳しく解説しています。是非ご覧ください。