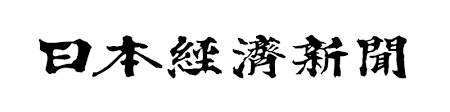マンションを購入したばかりの方は「管理組合」という言葉に馴染みがないかもしれません。「聞いたことはあるけれど実際どのように運営されている?」「自分はどのように関わっていく?」などと管理組合に対する疑問も多いのではないでしょうか。
管理組合を煩わしく感じている方もいるかもしれません。しかし管理組合の運営が破綻しているマンションは、資金不足により必要な修繕ができなくなったり市場価値が下がったりするなどの問題が生じてくるのです。
本記事ではマンションの管理組合の運営方法や管理会社との関係性、外部委託について解説します。管理組合の運営が破綻しやすいマンションの特徴と対策も紹介するため、マンションを購入した方または購入を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
マンションの管理組合ってなに?

「管理組合」とは、マンションの建物・敷地・附属施設を維持管理していくための団体です。管理費や修繕積立金といったマンションのお金の管理も管理組合でおこないます。
管理組合があることで、必要に応じて建物のメンテナンスや修繕ができたり、居住者間のトラブルを防止・解決することもできるなど安全で快適に住めるマンションを維持できるのです。結果、資産価値の向上にもつながります。
管理組合への加入は義務のため断れません。区分所有法では以下のように記されています。
「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」
区分所有者とはマンションの所有者のことです。マンションを購入した時点で区分所有法のもと、管理組合へ加入したことになります。
マンション管理組合の運営方法
マンションの所有者全員が管理組合の一員ですが、すべてを全員で議論して物事を決めていくのは現実的ではありません。
そこで組合員の中から役員(理事)を選出して検討事項を話し合い、全員で決議が必要な重要な事項は総会を開き、全区分所有者に賛否を問う形がとられています。
したがって、役員でなくても、区分所有者であれば、総会に参加し賛否を評するのが組合員として期待される活動内容になります。
「総会」で決議されるおもな内容
総会での決議の方法は多数決です。決議する内容によって、成立要件が議決権の過半数の「普通決議」と4分の3以上(一部例外あり)の「特別決議」に分けられます。
普通決議と特別決議の内容は下記の表のとおりです。
| 普通決議 | 特別決議 | |
| 開催時期 | 毎年1回新会計開始後2ヵ月以内 | 必要に応じ都度 |
| 内容 | 日常的な管理運営に関すること
・収支決算と事業報告 ・収支予算と事業計画 ・管理費、修繕積立金 ・長期修繕計画の作成、変更 ・役員の選任、解任 ・管理委託契約の締結 など |
例外的に生じた重大な議題
・管理規約の制定、変更または廃止 ・敷地及び共用部などの著しい変更 ・建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の共用部分の復旧 ・建物の建て替え など |
| 成立要件 | 組合員の議決権の過半数 | 組合員総数及び議決権総数の4分の3以上
※建て替え決議は5分の4以上 |
総会は年に1度必ず開催される定期総会と、必要なときだけ開かれる臨時総会があります。
定期総会で必ずあがる議題は「収支報告・事業報告」「管理会社との委託契約の更新」「収支予算」「役員の選出」の4つです。
役員(理事)の選出と業務内容
組合員であれば誰しもが管理組合の役員に選ばれる可能性があります。選出方法は管理組合によって異なりますが、立候補・推薦・輪番・抽選などです。
役員の任期は1~2年が一般的になっています。
役員のおもな活動内容は以下の3つです。
・マンション内で起きる日常的なトラブル対応や居住者相談を受ける
・理事会で収支計画やマンション内の課題などを討議する
・総会の準備をして開催する
【役員の構成】
役員は、理事長・副理事長・会計・監事などで構成されており、それぞれの役割があります。
総会を取り仕切る、管理組合の印鑑を保有し、工事の注文書などに署名捺印する
副理事長~理事長不在時の業務を代行する
会計~総会での決算報告、予算の説明など会計業務を担当する
監事~理事会の活動を監督し総会で報告する
役員の構成もマンションによってさまざまです。
管理組合の運営は管理会社がサポートしてくれる

管理組合の運営はすべてを組合員だけでおこなうわけではありません。管理組合は、管理委託契約書に基づき管理業務の一部を管理会社に委任しています。
たとえば、マンションの清掃や点検・管理人業務などの実務的な業務は管理会社の仕事です。また月ごとの収支状況の報告や、予算・事業計画案といった専門的な分野に関しても、管理会社から報告提案してもらえます。
ただし、管理会社はあくまでも管理組合のサポート役です。提案はしてもらえますが決定するのは管理組合のため、承認するかは理事会や総会でしっかり議論しなければいけません。
管理組合の運営が破綻しやすいマンションの特徴

管理組合の運営が破綻すると、管理費や修繕積立金の適切な運用ができなくなります。資金不足により、漏水が起きても修繕できない、外壁タイル剥落の危険があっても対処できないなど、安全で快適な暮らしができません。
住みにくくなったマンションには、次第に空室が増え、管理不全の悪循環に陥り、マンションはスラム化の一途をたどるのです。管理組合の運営が破綻しやすいマンションには、以下のような特徴があります。
・修繕積立金が足りない
・駐車場の空きを放置している
・管理意識・理事会の出席率が低い
順に詳しく解説します。
修繕積立金が足りない
築30年目頃までの長期修繕計画上では、問題なく修繕積立金を確保できる予定になっていても、30年以降まで計画に含めると赤字に転落するマンションが多くなります。
なぜなら築30年以降は、3回目の大規模修繕や機械式駐車場・エレベーターの更新など、お金がかかる工事が多いためです。
資金が足りなくなってから修繕積立金を値上げしても、すぐに資金は貯まりません。長期修繕計画に30年目以降に必要な工事が含まれていない場合は、早急に計画の見直しをすることをおすすめします。
すでに資金不足に陥っている場合は、劣化状態や過去の修繕履歴から優先順位を決めて、必要な工事を見極めましょう。
駐車場の空きを放置している
駐車場契約数が70%ほど減少している場合は、注意が必要です。駐車場の契約率は管理組合の収入(多くのマンションは管理費収入)に大きく影響します。
駐車場収入があることで管理費会計に余剰が出ると、修繕積立金に繰り入れて機械式駐車場の維持費に充当できます。しかし、収入が減ると維持費を捻出できません。
契約数が減少傾向になっている段階で、駐車場の設置台数は適正なのか、適正でない場合は一部平面化するのか、外部貸しするのかなど、施策を検討しておきましょう。
管理意識・理事会の出席率が低い
マンション管理に無関心な居住者が多かったり投資目的の外国人所有者が多かったりすると、役員のなり手が不足し十分な議論がされません。
実際に出席率が悪く理事会が開催されなくなったことで、総会にあげる議案を決められなくなり、定期総会すら開かれていないマンションもあります。
なり手不足を解消するには、役員の就任要件を緩和したり理事会の代理出席を認めたりするのがおすすめです。管理規約で「一親等以内の親族まで」など要件を緩和すると、区分所有者の子や親が参加できるようになるので、多様な考え方を取り入れるきっかけにもなるでしょう。
また無関心層をできるだけ少なくするための施策(外部の専門家による勉強会を開催するなど)を管理組合として取り組んでいくことも大切です。
マンション管理組合の運営は外部委託できる?

コストをかければ外部委託することもできます。「管理費に余裕があり手間をかけたくない」もしくは「役員のなり手不足などにより管理が危機的状況に迫られている」場合は、管理組合の運営を外部へ委託するのも一つの手です。
しかし、外部委託は利益相反行為に該当しやすいことが問題視されています。
2024年6月には「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」が改定されましたが、利益相反行為を完全に防げるまでには至っていないのが現状です。
以下で外部委託について詳しく解説します。
外部管理者方式(第三者管理方式)とは
管理組合の運営を外部に委託することを「外部管理者方式(第三者管理方式)」といいます。外部管理者方式は、管理会社が管理者になるパターンと管理会社以外の第三者が管理者になるパターンに分けられます。
さらに、外部管理者が理事会のメンバーの一員になるケース、理事会を設けず総会で監督(監査法人などの外部監査も)するケースなど形態もさまざまです。
現状は区分所有者の手間がかからない、理事会を設けないケースが主流になっています。
外部管理者方式を採用すると、役員のなり手不足を解消できるうえ、専門家が管理組合を運営するため修繕のタイミングなども適切に判断できるでしょう。
居住者の高齢化により役員のなり手がおらず管理組合がまったく機能していないような状況であれば、外部管理者方式を採用することで大きな効果が得られます。
参照:国土交通省「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」
外部管理者方式(第三者管理方式)利益相反に注意
外部管理者方式を検討する場合は、利益相反が起きやすいことを十分理解しておきましょう。利益相反とはある取引において、自分(自社)の利益になるように動くと、他方(管理組合)が不利益になることを意味します。
たとえば以下が外部管理者方式での利益相反行為です。
管理会社が管理者になる場合、自社と管理組合の管理委託契約の更新を自分たちで決められます。管理会社にとって管理委託費は利益になりますが、利益を追求しすぎると管理組合にとっては不利益です。
管理会社による責任施工方式(※)で大規模修繕する場合も同様に、利益相反が起きやすくなります。
※責任施工方式とは、工事前の劣化診断・工事設計・施工などすべてを1つの会社でおこなうこと
管理会社でない第三者に委託するにしても、管理会社の親会社や子会社、関連会社などに発注され割高な費用で工事が行われる可能性もあります。外部管理者方式を採用する場合は利益相反行為が起こりにくい仕組みをどう実現するのかといった課題が残ります。
ガイドラインの内容や問題点については下記動画で詳しく解説しているため参考にしてください。
マンションにおける外部管理者方式とは?マンション管理士が解説します
興味関心を高めて管理組合の運営を活性化させよう

マンションは購入者全員の資産です。管理組合の中心となって活動するのは役員ですが、マンション管理に興味関心をもつ所有者が少ないと盤石な体制とは言えず、築年数が古くなってきたときに管理組合の運営は破綻するでしょう。
管理組合の運営を外部委託する方法もあります。しかし、利益相反の危険性があったりコストがかかったりとデメリットも多いです。管理組合の運営が破綻する前に組合員みんなで関心を高め、マンション管理を見直して、できることから対策しておきましょう。
さくら事務所では、マンションの管理状況を診断し、向上に向けアドバイスする「マンション管理ドック」や「管理委託契約見直しサービス」や「管理会社変更サポート」など、管理組合運営についてもご相談に対応しています。
・役員のなり手が不足している
・総会への出席率が低い
・修繕積立金が足りていない
上記のような悩みがある場合はさくら事務所までご相談ください。第三者の専門家として、多種多様なマンションを見てきたコンサルタントが管理組合運営における問題点・改善点をアドバイスいたします。
下記動画でも破綻しやすいマンションの特徴を詳しく解説しているため、参考にしてください。
動画でお話ししていることQ1. 理事会が機能不全に陥るとどうなりますか?A. 総会での議案提出や工事発注ができず、マンション全体の管理が滞ります。結果として、必要な修繕が行えなくなります。 Q2. 修繕積立金が不足する主な原因は何ですか?A. 竣工時から一度も長期修繕計画の見直しをしていなかったり、築30年以降から発生する大掛かりな修繕工事を考慮していなかったことが原因です。早いうちから修繕積立金を見直さないと、取り返しのつかないことになります。 Q3. 建物の劣化を防ぐために管理組合が継続して行うべきことは?A. 適切な長期修繕計画の策定と物価の変動を計画に織り込むための定期的な見直しです。過去の修繕履歴や完成図書を保管し、次世代へ引き継ぐことも重要です。 |